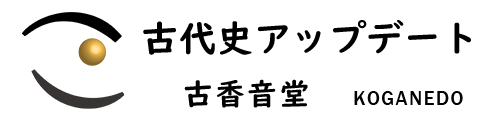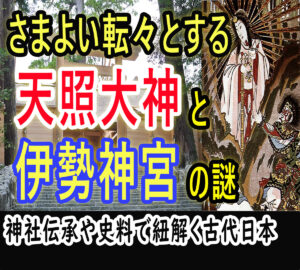諏訪大社とユダヤ教の謎!神社伝承や史料で紐解く日本古代史
日本最古と言われるのが諏訪大社です。
そんな諏訪大社とユダヤ教はどんな関係にあるのか?探っていきます。
■諏訪大社
諏訪大社は、日本最古の神社の一つで建御名方神を祀る式内社で旧官幣大社です。
上社:本宮・前宮、下社:秋宮・春宮の二社四宮が鎮座します。
全国に約25,000社ある諏訪神社の総本社です。
6年に一度行われる御柱祭や御頭祭で知られます。
上社・本宮の神体は守屋山と認識されています。
主祭神は、建御名方神です。
■守屋山
緑色凝灰岩でできている守屋山は、糸魚川静岡構造線と中央構造線が交わる地点にあります。
守屋山の東峰には、石祠があり、古絵図には「守矢大臣宮」「守矢大神」という名で記されています。
現在は南麓にある守屋神社(伊那市高遠町藤澤区片倉)の奥宮とされています。
物部守屋を祀る守屋神社が立っている伊那市片倉地区にも、物部守屋の子孫と名乗る守屋姓の家がたくさんあります。
また、山中には鍛冶技術を持った物部氏と関係があると思われる「鋳物師(いもじ)ヶ釜」の地名が残っています。
■守屋山とユダヤのモリヤ山
諏訪大社が守屋山を御神体としているのに対し、聖書のイサク伝承の「モリヤ山」と同じ名前であることを指摘する説があります。
ユダヤ教で「モリヤの神」といえば、聖書の天地創造の神・ヤハウェにあたるといいます。
ユダヤ人の伝承では、ソロモン王が神殿を建てたエルサレムのシオン山がモリヤであるとされています。
■御頭祭
4月15日に上社で行われる祭りは、「酉の祭り」「大御立座神事(おおみたてまししんじ)」「大立増之御頭」とも呼ばれています。
現在では、鹿や猪の頭の剥製が使用されていますが、江戸時代の菅江真澄の記録によると、白い兎を松の棒で串刺しにしたものや、鹿の頭75頭や猪の焼き皮と海草が串に刺さって飾られていたことが記されています。
また、鹿の脳和え、生鹿、生兎、切兎、兎煎る、鹿の五臓などが供されており、中世には鹿の全身が供され、「禽獣の高盛」と呼ばれていました。
さらに、諏訪大社の七不思議の一つとして「耳裂鹿」があります。
これは、生贄の鹿の中に必ず耳が大きく裂けたものがいるというものです。
「神長官守矢史料館」で御頭祭の再現展示をみることができます。
高さ1.5mほどの「御贄柱」(おにえばしら)というのがあり、太古には子供を柱に縛り付けて人柱として生贄にしたとか、真似をしただけとかの伝承が残っています。
まさに、狩猟採集生活が垣間見える儀式であり、縄文文化を特徴づける祭りです。
- 諏訪大社
- 守屋山
- 守屋山とユダヤのモリヤ山
- 御頭祭
- 守矢氏
- 御頭祭とイサク奉献伝承
- ミシャグジ神とイサク
- 中央構造線
- 中央構造線上に多くの神社がある理由
- 諏訪大社の起源説話
- 大国主命と出雲国譲り
- 大国主命と建御名方神との力比べ
- フネ古墳
- 美保神社
- 穂高神社
- まとめ
日本古代史の謎を紐解き、すこしでも本来の日本建国の姿を再現できればと思い、ご紹介させていただきました。
このチャンネルでは、独自の視点から見た歴史について発信しています。
この動画は下記の音声読み上げソフト、画像、動画、音楽を使用しています。
・Wikipedia
・Adobe stock
・YouTube オーディオライブラリ
・VOICEPEAK
【参考書籍】
・『記紀以前の資料による古代日本正史』原田常治 著
・『日本書紀上下』宇治谷孟 著 講談社学術文庫
・『古事記上中下』次田真幸 著 講談社学術文庫
・『続日本紀上下』森田悌 著 講談社学術文庫
・『古代史が解き明かす 日本人の正体』関裕二 じっぴコンパクト新書
・『古代史おさらい帖』森浩一 著 ちくま学芸文庫
・『聖書の隠された日本・ユダヤ封印の古代史』ラビ・マーヴィン・トケイヤー 著 徳間書店
・『縄文の神が息づく 一宮の秘密』戸矢学 著 方丈社
・『先史・古代の気候と社会変化』 中塚武 著 臨川書店
・『「縄文」の新常識を知れば日本の謎が解ける』 関裕二 著 PHP新書
関連記事:卑弥呼と天照大神